「卵は一つのカゴに盛るな」というように、投資でリスクを抑えるには「分散」が有効な方法です。経済や市場に影響を与える要素が複雑化し、将来の予想がますます難しくなるなかで、性質の異なる資産を持っておく意味がより色濃くなっています。
投資といえば、まず株式や投資信託など金融資産を保有する方が多くみられます。そこでリスクを分散するなら、実物資産である不動産が選択肢のひとつとして挙げられるでしょう。
本記事では、不動産を活用した分散投資の大枠を整理し、不動産クラウドファンディングにおける分散投資について紹介します。
分散投資の選択肢としての不動産
まずは、いま分散投資が必要とされる背景を整理するとともに、資産としての不動産の特徴と、不動産投資の手法をみていきましょう。
分散投資の必要性
相場の動きを完璧に予測できる人はいません。もともと難しいものですが、近年は経済情勢や各市場を動かす要因が複雑化しており、予想はますます困難になっています。
インフレや金利、為替、地政学リスクだけでなく、SNSの発展やAIの登場なども市場に影響を与える要素です。
こうしたなかで、日経平均、米国のS&P500、ナスダック総合指数はいずれも、コロナ禍あたりで下落したものの、長期的にみれば右肩上がりで上昇を続けています。最近は「買われすぎている」「加熱している」との指摘もみられ、今後いつか、調整局面に入るかもしれません。
いつ、何をきっかけに市場が上昇・下落するのかがわかりづらい現在の状況において、「安全」といえる資産の見極めは困難でしょう。
だからこそ、資産の分散によるリスクの軽減が大切だといえます。
不動産の魅力
不動産は株式とも債券とも異なる特徴を持つ資産です。
株式は企業の業績や景気動向、金融政策の影響を強く受け、値動きが活発で、流動性が高い資産です。ハイリスク・ハイリターンで、売却益を狙う投資に適しています。
一方、債券は発行体の信用力や金利水準に左右され、ローリスク・ローリターンで安定した利息を中心に得ていく資産です。
不動産の価格は、需要と供給、人口動態や地域の再開発といった要因で変動します。投資としてはミドルリスク・ミドルリターンの性質を持ち、長期的に賃料収入を得ながら、出口戦略次第では売却益を得られる可能性があります。
このように、不動産は株式とも債券とも異なる特徴を持つため、金融資産のみで運用している方にとって有効な分散先だといえるでしょう。
ただし、不動産(マンションやアパート)を自分で取得・運営するには、まとまった資金と手間が必要です。ローンを利用できれば手元資金は抑えられますが、投資額自体が大きいため、ほかの資産とのバランスが取れないケースも考えられます。
また、オーナー業の手間がかかるため、金融資産への投資よりも実務の負担が大きく、投資に取り組むハードルの高さがネックとなりがちです。
不動産クラウドファンディングの魅力
不動産投資の資金面と負担面のハードルを下げられる方法が、不動産クラウドファンディングです。不動産クラウドファンディングでは、運営事業者と投資家が共同出資で不動産を取得します。そして一定期間の運用後、投資家には配当金が分配され、出資金も戻ってくるしくみです。
不動産クラウドファンディングの特徴は大きく2つあります。
まず、1口1万円と少額から出資できるファンド(案件)が多い点です。出資額を柔軟に決められるため、手元資金の具合やほかの保有資産とのバランスがとりやすいといえます。
次に、オーナー業が不要な点です。物件探しから入居者対応、建物の維持管理、修繕、売却まで、すべて事業者が担います。実際の不動産売買も事業者がおこなうため、投資家は不動産オーナーにはなりません。
また、運用が始まると満期まで値動きはありません。ファンドに出資したら、満期までほったらかしで資産を運用できる負担の小ささが魅力です。
もちろん、注意点も2つあります。
第一に、ひとつの物件に対してひとつのファンドが組成されるため、ファンドごとに物件のあるエリアや物件の種類、運用期間が異なり、リスクも異なります。
第二に、基本的に運用中の解約ができません。このため一度出資すると、満期まで資金が拘束されます。
したがって、不動産クラウドファンディングにおいても複数のファンドに出資し、リスクや資金の拘束期間を分散しておくと安心です。
不動産クラウドファンディングでの3つの分散
では、不動産クラウドファンディングではどのような視点で分散投資に取り組めばよいでしょう。ここでは、不動産クラウドファンディングで意識したい3つの分散方法をみていきましょう。
エリアの分散
不動産投資では物件のある場所が収益性に大きく影響し、とくに都心部と地方都市では異なる傾向がみられます。
都心部は需要が安定しているため入居率も高く、収益の安定性が期待できます。しかし、その分物件価格は地方都市よりも総じて高く、利回りは相対的に低めです。
一方、地方都市では物件の購入価格が抑えられる分、利回りは都心部の物件よりも高めに設定される傾向があります。ただし、地方都市は地域によっては人口減少や空室リスクが大きいため、物件選定の難易度は高くなります。ニーズのある物件を選べれば問題ありませんが、需要が低いと入居がつかない、予定どおり売却できないなども起こりやすいでしょう。
こうしたエリアごとの特徴を踏まえて、都心か地方かの二者択一ではなく、複数エリアへの分散をおすすめします。なぜなら日本は自然災害が多く、いつ、どこで災害が起こるかわからないからです。
複数のエリアに分散しておけば、万が一ある地域で災害があっても、資産全体への影響を抑えられます。
時間の分散
不動産クラウドファンディングでは、基本的に運用期間中の途中解約はできません。したがって、資金の拘束期間やタイミングを意識したファンド選びも大切です。
不動産クラウドファンディングのファンドは、一般的に運用期間が1年以内のものが短期、1年以上になると長期に分類されます。
短期ファンドは、運用期間の短さから、市場の急激な変動に巻き込まれるリスクも低めです。ただし、ファンドの利回りは年利表示である点に注意しましょう。実際に受け取る配当金は運用期間に応じて計算されます。
くわえて、短期ファンドへの投資では、満期を迎えた後に次の投資先を探す手間が増える点も考慮しましょう。
一方、長期ファンドは運用期間が長い分、より高い収益を期待できます。もちろん市況の変動に影響を受けやすくなるものの、下落だけでなく上昇の恩恵を受けられる可能性もあります。しかし、長期ファンドばかりだと拘束される資金が多くなるため、急に入り用になったときにも対応できるよう計画性が重要です。
現在の不動産クラウドファンディングは短期ファンドが主流で、長期ファンドは数が少ない状況ですが、うまく組み合わせて資金の拘束を分散できるとよいでしょう。
事業者の分散
株式や投資信託はどの証券会社で購入してもその商品性は変わりませんが、不動産クラウドファンディングの場合は事業者ごとにファンドの特徴や傾向が異なります。
たとえば、強みとするエリアや、投資家保護のしくみである優先劣後方式の劣後出資(事業者の出資)の割合、配当原資の考え方などです。ハイリスクだが高利回りのファンドを多く提供する事業者もあれば、利回りはほどほどでも堅実なファンドを中心に提供する事業者もあります。
このため、複数の事業者を利用すると、自然と資産やリスクの分散につながりやすくなります。
また、不動産クラウドファンディングはまだ歴史の浅い投資手法です。
ひとつの事業者を集中して利用していると、万が一その事業者で不祥事や経営トラブルが生じたときに、資産が大きな影響を受けるリスクもあります。
とはいえ分散しすぎても管理が大変になってしまうため、利用しやすい2、3社を決めておくとよいでしょう。
選定にあたっては、事業者の信頼性や実績、ファンドの運用実績、情報開示の分かりやすさなどを確認すると安心です。
不動産クラウドファンディングのポートフォリオの考え方
不動産クラウドファンディングにおける3つの分散方法を踏まえて、ここではファンドの組み合わせ方を具体的に考えていきましょう。
堅実枠とチャレンジ枠の設定
おすすめは「堅実枠」と「チャレンジ枠」の2枠に分ける考え方です。
堅実枠で選ぶファンドは、都心の住居系物件で運用する短期のファンドが代表例です。住居系の物件は賃料収入が安定しやすい点が特徴です。
他方、チャレンジ枠では、ややリスクをとる代わりに比較的高い利回りを期待できるファンドに出資します。たとえば地方都市の商業施設やホテルを対象とした長期ファンドなどが挙げられます。
安定性を重視したい方は堅実枠を多めに設定し、ほどよく収益も期待したい方は堅実枠とチャレンジ枠のバランスを重視して組み合わせるとよいでしょう。
よりリスクの小さいファンドを選ぶ方法
不動産クラウドファンディングの平均的な予定配当率は5〜6%程度で、ファンドごとにリスクとリターンは異なります。金融資産への投資と同じく、予定配当率が高いファンドほどリスクも高い傾向にあります。
よりリスクを抑えたい場合は、インカムゲイン型のファンドがおすすめです。
インカムゲイン型とは、賃料収入を配当原資とするファンドです。
一方、不動産の売却益を配当原資とするファンドはキャピタルゲイン型に分類されます。不動産の高値での売却が前提となるためリスクが高く、その分利回りも高めのものが多くみられます。
もちろん、インカムゲイン型も絶対に安心とはいいきれませんが、心配な方はチャレンジ枠でもインカムゲイン型に限定する方法もひとつの選択肢です。インカムゲイン型でも、予定配当率が比較的高いファンドも提供されています。比較サイトなども活用して、いろいろなファンドを見比べるとよいでしょう。
地方×堅実タイプの不動産クラウドファンディング「みらファン」
「エリアの分散」でお伝えしたように、地方よりも都心部の物件のほうが収益の安定性が期待できます。地方はリスクが高めといわれるなか、「みらファン」は東海エリアの物件をおもな対象とし、堅実性も兼ね備えたファンドを提供しています。
そうしたファンド組成が可能な理由は、運営会社である「みらいアセット」が愛知県名古屋市に本社を置いているためです。地域特性を把握したうえで物件を厳選しており、償還済みの12件はすべて予定配当を達成。元本割れや償還の遅延も一度も発生していません。
また、「みらファン」はファンドの設計思想にも特徴があります。
投資家を優先する「優先劣後方式」を採用し、多くのファンドで劣後出資比率は20%と、厚めの水準に設定しています。くわえて、これまで組成した21件すべてが、賃料収入を配当原資とするインカムゲイン型のファンドです。
地元企業ならではの知見と、安定性を重視する設計思想により、地方都市の物件でもローリスクを実現しています。
まとめ
経済情勢や各市場の動きが複雑化するなかで、保有資産を分散する重要性が増しています。金融資産とは性質が異なる不動産は、リスク分散の一役を担う資産といえるでしょう。
また、不動産投資においても分散投資はリスクの低減に有効です。しかし実物の不動産で分散投資をするには多額の資金が必要となり、実現は容易ではありません。
その点、不動産クラウドファンディングなら1口1万円から始められ、無理なく分散投資に取り組めます。
なかでも地方×堅実が特徴の「みらファン」なら、エリアの分散効果と、安定性とリターンの両立を期待できます。
そのほか、「みらファン」の特徴は以下のとおりです。
- 投資したい物件を選ぶことができる
- 少額から手軽に投資が可能
- 利回りが比較的高い
- 不動産管理に関する手間が不要
- リーシングに関する対応は事業者側が行う
- 運用中の資金の上下が無い
- 優先劣後構造で投資家を保護
「みらファン」を分散投資の選択肢として、ポートフォリオに組み入れてみませんか。
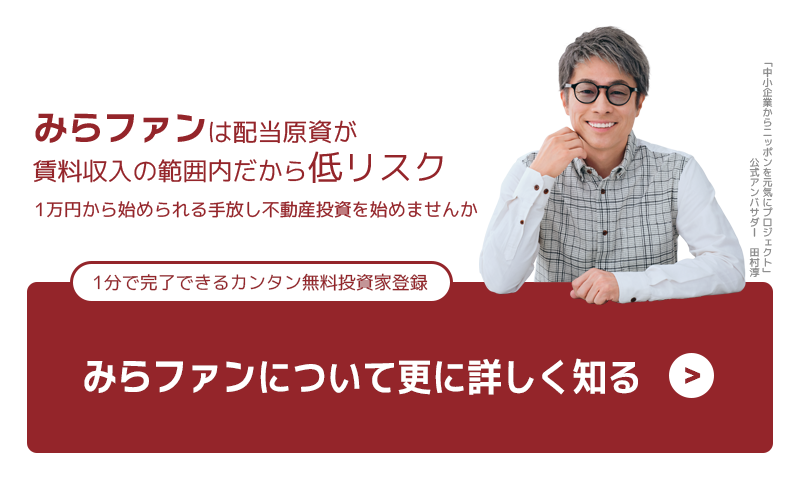











コメント