不動産投資とクラウドファンディングを掛け合わせた「不動産クラウドファンディング」が、着実に市場を拡大しています。2024年の新規ファンド数は875件、出資額は1,763億円にのぼり、2019年と比べてファンド数は8倍以上、出資額は実に約51.5倍と、指数関数的な成長をみせています。
事業者やファンドがどんどん増えるなかで、何を選ぶべきか悩んでいる方も多いでしょう。安定志向の方に適した選択肢のひとつが、当社が運営する「みらファン」です。
本記事では、不動産クラウドファンディング全体の傾向と比較しながら、「みらファン」の特徴を整理してご紹介します。
投資対象エリア:東海地方が中心
不動産クラウドファンディングの投資対象物件のうち、約半数が首都圏に集中しています。なぜなら、東京都心の物件は比較的収益を見込みやすいためです。続いて、大阪を中心とする近畿地方、名古屋を中心とする東海地方がそれぞれ13%程度を占めます。
一方で「みらファン」の投資対象は、東海エリアを中心に香川県や群馬県など、地方都市の物件です。すでに別の不動産クラウドファンディングを利用している方にとっては、エリア分散を図れます。
地方都市にこだわる理由は、運営会社である「みらいアセット」の代表自らの思いにあります。過去に中小企業のコンサルティングに従事していた際、「物事は東京中心に進み、地方は後回しになっている」と感じた経験がきっかけです。
そこで、名古屋に本社を置く「みらいアセット」が地元志向で取り組める事業を模索し、不動産クラウドファンディングにたどり着きました。
運営事業者:経営層は銀行出身
「みらいアセット」は2004年に「みらいホールディングス」の子会社として設立された不動産コンサルティング企業です。不動産クラウドファンディングのほか、不動産の売買や仲介、管理も手がけています。
「みらいホールディングス」は、もともと中小企業の経営支援を目的として、2003年に現代表が個人創業した会社です。現在は6社からなるグループ体制となり、M&A支援やマンスリーマンション・シェアハウスの運営、ホテル事業などを展開しています。
みらいグループの大きな特徴は、経営層に銀行出身者が揃っている点です。
代表取締役はいずれも銀行の出身で、法人融資や資金調達、経営戦略に関する豊富な知見を持ちます。
銀行勤務で培った堅実な判断力や実行性のある課題解決力が強みであり、提供するファンドも安全性や、リスクとリターンのバランスを重視して設計しています。
【関連記事】
不動産クラウドファンディング「みらファン」を運営するみらいアセットはどんな会社?
リスク・リターン:インカム型で安心性を重視
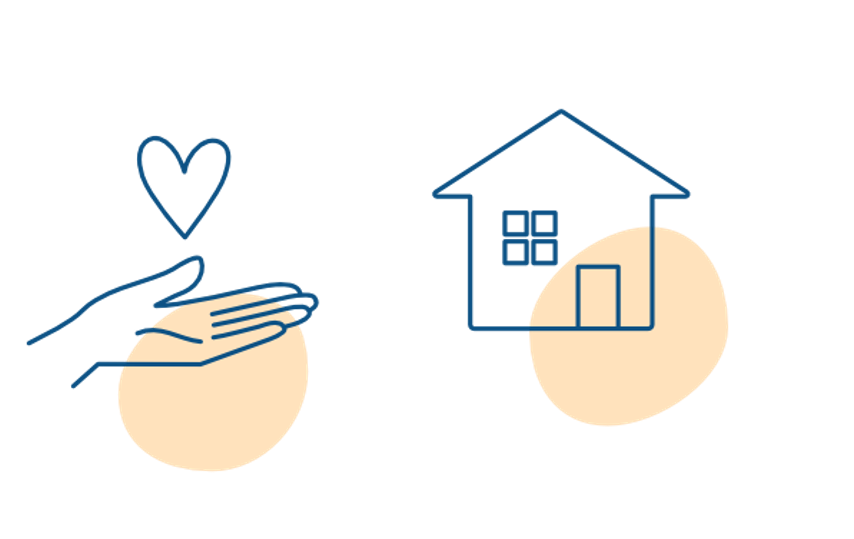
では、ファンドの設計にはどういった方法があるのでしょうか。
たとえば、配当原資を確保する方法により「インカム型」と「キャピタル型」のファンドに大別され、両者を組み合わせた「ハイブリッド型」も存在します。
インカム型とキャピタル型では仕組みやリスクが大きく異なり、どちらを多く取り扱うか、事業者の特徴が表れやすいポイントでもあります。
「みらファン」は一貫して純粋なインカム型ファンドを提供していますが、ここではそれぞれの概要を整理しておきましょう。
インカム型:ローリスク・ローリターン~ミドルリターン
インカム型は賃料収入から配当をおこなう設計です。空室リスクはあるものの、法人テナントとの間で退去申請期間を長く設定するなどの工夫によって安全性を高めているファンドもみられます。なお、「みらファン」は一部ファンドではマスターリース契約を活用して一括借り上げや賃料保証などで安全性を高めています。
2025年9月時点で、不動産クラウドファンディングのインカムゲイン想定利回りは平均で4%弱(※)とみられる一方、「みらファン」のこれまでの平均利回りは約6%程度と好水準です。安全性・リスク抑止を重視したローリスク・ミドルリターンのファンドを提供しつづけています。
※不動産CFデータベース | 一般社団法人不動産クラウドファンディング協会 より筆者集計
キャピタル型:ハイリスク・ハイリターン
キャピタル型は不動産の売却益を配当原資とする設計です。売却益を得る方法は以下のように複数あります。
- 土地を取得して新たに建物を建てる
- 建物を取得してリノベーションする
- 建物を解体して更地にし、再開発可能な土地にする など
いずれも、土地や建物を取得し、その価値を高めて売却して利益をあげる手法です。その過程では、資材価格や人件費の上昇による工事費の上昇、工事のトラブルや長期化、権利関係の問題など、インカム型にはないリスクが伴いますし、必要な費用も大きくかかることから取得額よりも大きく値段を上げた状態で売却する必要があります。
リスクが高い分インカム型よりも利回りが高い傾向にあり、近年では10%を超えるものも多く、利回り競争の過熱感がみられます。業界内では想定利回りの根拠の開示など、透明性の向上が検討されているところです。
投資は自己責任ですので、しくみやリスクをよく理解したうえで事業者やファンドを選びましょう。
劣後出資比率:過去実績で20%
ファンド設計の点でもうひとつ、「優先劣後出資」があげられます。
投資家だけでなく事業者もともに出資し、万が一損失が出た際にはまず事業者側が損失を負担するしくみです。
「みらファン」は20%の出資比率を標準設定としていますが、優先劣後出資を採用するかどうか、また出資比率はファンドや事業者ごとに異なります。
ここでは、優先劣後出資による投資家のメリットや、事業者が劣後出資をおこなう意義について簡単に解説します。
優先劣後出資とは
優先劣後出資を簡単に説明すると、投資家だけでなく不動産クラウドファンディング事業者もファンドに出資することです。もしも損失が出た場合には、事業者からその損失を負担します。損失の額が事業者の出資額以内に収まれば、投資家には損失の影響が及ばず、元本が守られるしくみです。
このしくみでは、事業者は「劣後出資者」として位置づけられ、事業者の出資金を「劣後出資金」とも表します。例として、総額1億円のうち事業者が2,000万円を出資しているファンドでは、劣後出資比率が20%となります。
なお、事業者の出資は法制度で義務づけられているものではありません。劣後出資比率が0%のファンドもあれば、30%を超えるものもみられます。「みらファン」は20%を標準設定としています。
劣後出資の意義
劣後出資は、投資家にとってはファンドの安全性が高まる嬉しいしくみです。
しかし事業者にとっては投資家よりも高いリスクを背負うことにほかならず、負担が非常に大きい取り組みです。
裏返せば、劣後出資をしなければ、ファンドで損失が生じても事業者は損失を被らずにすみます。現にキャピタル型のファンドでは劣後出資比率が0%のものも多くみられます。
ではなぜ、そこまでのリスクを背負って事業者は劣後出資をするのでしょうか。
みらファンが劣後出資を行うのは、優先出資者である投資家のリスクを少しでも軽減し、安心していただくためです。
事業者自身も同じ船に乗り、一緒にリスクを背負うことは投資家にとっては事業者が同じファンドに対して同じリスクを背負うこととなるため、責任ある運営が行われることがメリットです。また、劣後出資はその事業者がそれだけのリスクを背負える財務基盤を持っているからこそおこなえるものです。
優先劣後出資のしくみだけでなく、その奥にあるリスクへの高い意識や事業者の財務基盤も、投資家にとっては評価ポイントとなるでしょう。
想い:地方を応援したい
不動産クラウドファンディングを運営する目的は事業者によってさまざまです。
まず、不動産会社がバックエンド商品である実物不動産の販売につなげるマーケティング施策として活用するケースがあげられます。
次に、クラウドファンディング本来の役割である「資金を必要とする人と投資家をつなぐ架け橋」として運営するケースもあります。
このうち「みらファン」の目的は後者です。だからこそ、誰でも参画しやすいように最低投資額を1万円に設定しています。
「みらファン」は、先述したとおり「東京を中心に物事が進み、地方は後回しになっている」という代表の課題意識から生まれました。
地方の衰退は都市部に暮らす人たちにとっても無関係ではありません。たとえば食料やエネルギーの多くは地方で生産されており、わたしたちの生活は地方に支えられているからです。
こうした地方を応援したいとの思いで、当社は「みらファン」を運営しています。
当社が地方の優良物件を見つけ出し、投資家は「みらファン」を通じて地方にお金を投じる。その資金で地方の大切な不動産が再生し、投資家は配当金を受け取り、増えたお金でまた別の不動産に投資する。
これが、「みらファン」が目指すお金の循環です。
地域の大切な物件が息を吹き返し、その地域全体が元気になり、元気のある地域が増えることを目指しています。
【関連記事】
不動産クラウドファンディング「みらファン」が大切にしている3つの思い
まとめ
不動産クラウドファンディングとひと口にいっても、ローリスク・ローリターンなファンドからハイリスク・ハイリターンなファンドまでさまざまです。
そのなかで「みらファン」は堅実さや安全性を重視した設計にこだわり、ローリスク・ミドルリターンのファンドを提供しつづけています。
また「地方を応援したい」との思いから、これまですべてのファンドで地方都市の物件を投資対象としてきました。
「みらファン」はエリア分散の選択肢として活用しやすいファンドです。
- 投資したい物件を選ぶことができる
- 少額から手軽に投資が可能
- 利回りが比較的高い
- 不動産管理に関する手間が不要
- リーシングに関する対応は事業者側が行う
- 運用中の資金の上下が無い
- 優先劣後構造で投資家を保護
「みらファン」で1口1万円から不動産投資を始めてみませんか。
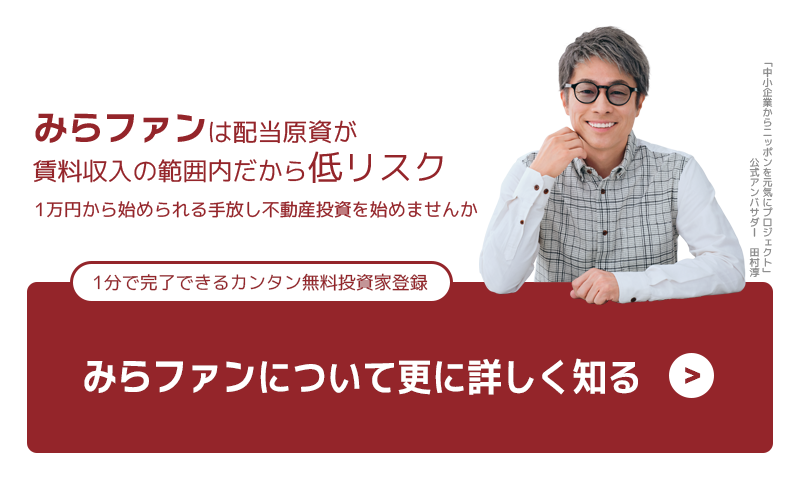











コメント