不動産クラウドファンディングは投資の一種ですが、株式や投資信託、実物不動産への投資とは税金のしくみが異なります。
基本的に、配当金は源泉徴収によって納税が完結するものの、確定申告が必要になるケースもある点には注意が必要です。
本記事では、不動産クラウドファンディングの課税のしくみや確定申告の必要性について整理するとともに、節税に関しても解説していきます。
配当金は基本的に源泉徴収で納税が完結
はじめに、不動産クラウドファンディングでは配当金のみが課税対象ですが、出資元本には課税されません。
多くのファンドで配当金は雑所得に分類され、受け取り時に20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)が源泉徴収されます。投資家のアカウントには税金が天引きされた後の金額で配当金が入金されるため、配当金の受け取り時にはすでに納税が完結しています。したがって、原則として確定申告の必要はありません。
ただし、所得の状況次第で確定申告が必要な場合があるほか、申告によって税金の還付を受けられる場合もあります。
確定申告が必要となるケース
ではどのような場合に確定申告が必要になるのでしょうか。所得の区分・税率に関する注意点とともに整理していきましょう。
確定申告が必要となる代表例4パターン
確定申告が必要となる代表的なパターンは下記のとおりです。
- 個人事業主をはじめ、もともと確定申告の義務がある人
- 所得控除(医療費控除、ふるさと納税の寄付金控除など)の適用を受けたい人
- 給与収入が年間2,000万円を超える人
- 給与収入がある人のうち、給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超える人
また、4番の「給与所得・退職所得以外の所得」の具体例としては、以下があげられます。(事業的規模や取引形態により例外もあります。)
- 副業の報酬
- フリマアプリやネットショップでの販売収益
- 暗号資産の売却益
- 不動産クラウドファンディングの配当金
- 不動産の賃料収入 など
これらの合計が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。
雑所得に関する2つの注意点
所得といっても全部で10種類の区分があり、不動産クラウドファンディングの配当金の多くはこのうち「雑所得」に分類されます。
もう少し細かく説明すると、不動産クラウドファンディングは任意組合型と匿名組合型の2種類のスキームに大別され、「みらファン」も含めて主流は匿名組合型です。
この匿名組合型の不動産クラウドファンディングの配当金が雑所得となります。
ここで、雑所得に関して、確定申告や納税にあたり知っておきたい2つの注意点をみていきましょう。
赤字の相殺について
雑所得には、不動産クラウドファンディングの配当金のほか、副業の報酬や、フリマアプリ・ネットショップでの販売収益、暗号資産の売却益が該当します。
雑所得で赤字が出た場合には、同じ雑所得内であれば黒字と赤字を相殺できます。
たとえば、不動産クラウドファンディングで年間25万円の配当金を受け取ったとすると、20万円を超えているため本来は確定申告が必要です。
ここで、もし同年に暗号資産取引で30万円の損失が出ていれば、確定申告の必要がなくなります。なぜなら、暗号資産取引の赤字と配当金を相殺できるためです。
25万円-30万円=▲5万円と、雑所得全体ではマイナスになります。
ただし、雑所得の赤字は給与所得などほかの所得とは相殺できません。
損益通算はあくまで雑所得内に限り可能で、所得区分をまたげない点に注意しましょう。
所得税率について
給与所得に加え、雑所得や不動産所得などで所得が多くなると、所得税が高くなる可能性があります。日本では所得税に超過累進税率が採用されており、対象となる所得が増えるにつれて所得税率が段階的に高まるしくみのためです。
税率は5%~45%まで7段階に分かれ、たとえば695万円以上900万円未満の所得に対する税率は23%ですが、900万円以上1,800万円未満の所得には33%が適用されます。
配当金などで所得額が増えると、思わぬ税負担となるおそれがある点を頭に入れておきましょう。
所得税の環付が受けられる可能性がある人
課税対象となる所得金額が330万円未満の人は、確定申告によって所得税の還付を受けられる可能性があります。この理由も、所得税に超過累進税率が採用されているためです。
「課税対象となる所得金額」とは、総合課税の対象となる所得の合計から所得控除を引いた額です。
- 総合課税の対象となる所得:給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得など
- 所得控除:基礎控除や配偶者特別控除、医療費控除、生命保険料控除など
これらによって計算される「課税対象となる所得金額」が330万円未満の場合、適用される所得税率は5%~10%です。一方、不動産クラウドファンディングの配当金は20%で源泉徴収されます。
このため、所得の金額や所得控除の内容によっては、確定申告をすれば源泉徴収で払いすぎていた税金が還付されるかもしれません。
不動産クラウドファンディングでの節税は難しい
不動産クラウドファンディングは、税金面での優遇を受けられる投資ではありません。
節税効果を重視するなら、NISAやiDeCoといった制度を利用するか、実物不動産のように経費計上が可能な投資が選択肢となるでしょう。
ここでは、不動産クラウドファンディングで節税が難しい理由を、ほかの投資と比較しながら解説していきます。
NISAやiDeCoと違って税優遇がない
NISAは運用益や配当金・分配金が非課税となる制度です。
また、iDeCoでは運用益が非課税のほか、掛金は所得控除の対象で、受け取る年金や一時金も一定の所得控除の対象となります。
一方、不動産クラウドファンディングの出資金や配当金に対してはこうした税制上の優遇はなく、配当金の全額が課税対象となります。
しかし、不動産クラウドファンディングならNISAやiDeCoでは難しい不動産への投資が可能です。節税目的ではなく分散投資の一環として併用するとよいでしょう。
実物不動産への投資と違って経費が発生しない
実物不動産への投資では、減価償却費や修繕費、固定資産税など、多くの経費を計上できます。これらの経費は賃料収入から差し引けるため、結果として所得額を圧縮でき、節税につながる点が特徴です。実際に、節税対策の一環として不動産投資に取り組む人も多くみられます。
その反面、不動産クラウドファンディングでは投資家が不動産を直接所有するわけではないため、基本的に経費も発生しません。したがって、経費により所得を圧縮して税負担を軽減するような節税効果は見込めませんが、税務処理や物件管理といった運用上の手間がなく、手軽に始めることが可能です。
不動産投資に取り組んでみたいが、実物不動産を取得する資金的余裕がない方は、1口1万円から取り組める点で不動産クラウドファンディングを選ぶとよいでしょう。
まとめ
不動産クラウドファンディングにはNISAやiDeCoのような税優遇制度がなく、節税効果を期待できる投資ではありません。
しかし多くのファンドで配当金は支払時に源泉徴収され、確定申告が不要で手軽に不動産投資に取り組める点が大きな魅力です。
NISAやiDeCoと組み合わせて、分散投資の一環としての活用がおすすめです。
当社が提供する不動産投資型クラウドファンディング「みらファン」なら、1口1万円から出資していただけます。
- 投資したい物件を選ぶことができる
- 少額から手軽に投資が可能
- 利回りが比較的高い
- 不動産管理に関する手間が不要
- リーシングに関する対応は事業者側が行う
- 運用中の資金の上下が無い
- 優先劣後構造で投資家を保護
「みらファン」で手軽に不動産投資を始めてみませんか。
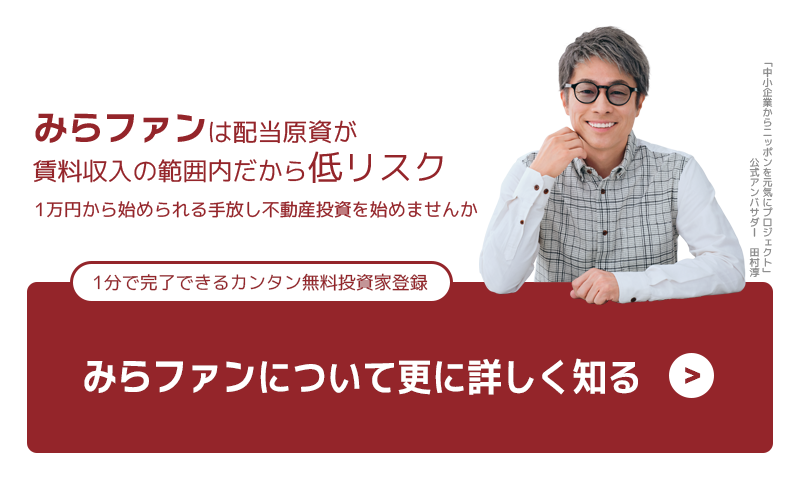











コメント