投資信託を通じた投資も含めて、株式を資産形成の中心に据える投資家が多くみられます。株式は期待リターンが高く、魅力的な資産クラスといえます。しかしその分値動きも大きいため、余裕資金であってもその全額を投じるわけにはいかないでしょう。
そこで、分散先としておすすめしたい資産クラスが不動産です。なかでも不動産クラウドファンディングであれば、少額から不動産投資に取り組めます。
本記事では、株式投資の分散先として不動産クラウドファンディングを活用する3つのメリットを解説します。
株式との組み合わせで不動産に注目すべき理由
「資産三分法」という考え方をご存じでしょうか。
異なる特性を持つ3種類の資産をバランスよく保有し、リスクを抑えながら収益も高めようとする伝統的な手法です。3種類の資産とは、一般的には現預金・有価証券(株式)・不動産とされています。
また、特性の違いとして、安全性・収益性・流動性の3要素がよく比較されます。
- 安全性:元本や利子の支払いの確実さ
- 収益性:期待できる収益の大きさ
- 流動性:換金のしやすさ
現預金は安全性と流動性には優れますが、収益性(利息収入)はほとんど期待できません。株式は値動きが大きく安全性には欠けますが、高い収益性を持ち、流動性も比較的高いといえます。そして不動産は賃料収入の性質から安定性は比較的高く、情勢によっては賃料収入に加えて売却益による収益も期待できます。ただし売買に時間がかかるため、流動性は低い資産です。
| 現預金 | 株式 | 不動産 | |
|---|---|---|---|
| 安全性 | 高い | 低い | 中程度 |
| 収益性 | 低い | 高い | 中程度~高い |
| 流動性 | 高い | 中程度~高い | 低い |
それなら、株式に投資しておけば効率よく、資産をより多く増やせるのでは?と思うかもしれません。
たしかに株式は3種類のなかでは長期的な収益性がもっとも高いといえます。しかし値動きの激しさを踏まえると、余裕資金とはいってもその全額を株式に投じようとは思いにくいのではないでしょうか。とくに運用できる期間が短い方や、養う家族が多い方、収入や資産が少ない方、投資経験が浅い方などは、受け入れられるリスクが大きくないといえます。「もしも」を考えると、株式のような高リスク資産の割合はあまり多くできません。
かといって余裕資金を現預金で持っていると、今度はインフレに負けてしまいます。そこで、安定性と収益性が比較的高い「利回り資産」である不動産が候補にあがります。
不動産は1件あたりが高額なため、従来は保有できる個人投資家が限られていました。しかし金融テクノロジーの発展や法整備により、不動産投資のハードルは大きく下がりました。不動産クラウドファンディングや不動産小口化商品といった形で、現在は1口1万円から不動産への投資が可能になっています。
<参考記事>
社会貢献にもつながる「不動産クラウドファンディング」のしくみとは?
ここからは、株式投資の分散先として不動産、不動産クラウドファンディングを活用するメリットを3つ紹介していきます。
メリット1. 安定したインカムゲインが得られる

現預金・株式・不動産のなかで、長期的な期待リターンがもっとも高い資産クラスは株式です。株価の上昇によって大きな売却益(キャピタルゲイン)を得られる可能性があるためで、株式投資の最大の魅力でもあります。それだけ株価の動きは活発であり、株式は値動きをうまく利用してキャピタルゲインを得る資産といえるでしょう。
裏返せば、株価が大きく下振れる可能性もあるため、収益の安定しづらさも特徴です。
なかには配当金を目的に株式を保有する人もみられますが、業績によっては減配や無配になり得ます。いずれにしても収益の不確実性は高いといえます。
その点、不動産は比較的安定した賃料収入(インカムゲイン)を得られる資産です。入居者やテナントから得られる賃料は、景気や市況の影響を受けつつも、株価ほどは大きく揺れ動きません。株式のみでは実現しにくい定期的な収益を積み上げられ、投資効率の向上を期待できます。
不動産クラウドファンディングでは、この賃料収入を原資とする配当金を受け取れます。例として「みらファン」の平均配当利回りは年5%~6%程度です。
相場の動きを読みながら売却益を狙う株式投資とは対照的に、基本的には実物の不動産と同様、定期的かつ安定的なインカムゲインを得ていく投資といえます。
なお、公的年金を運用するGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)も、株式・債券での運用を中心としながら、不動産をポートフォリオに組み入れています。安定的に賃料収入を得られ、ある程度の利回りを期待できる投資戦略を重視しているためです。
メリット2. 実物資産でインフレに強い
インフレとは、モノやサービスの価格が継続的に上昇していく状態を指します。生活費がかさむ一方、現預金のように利息がほとんどつかない資産は実質的な価値が目減りしてしまいます。
不動産は土地や建物といった形ある「物」です。インフレ局面では不動産価格や賃料が上昇しやすい傾向がみられます。メインの収益となる賃料収入も増える可能性がある点は、不動産が持つ大きな強みといえるでしょう。
一方の株式もインフレに強いといわれることがあります。
単純な見方をすると、モノやサービスの値段が上昇すれば企業の収益も増え、業績が伸び、株価が上昇すると考えられるためです。
しかし実際には、インフレの要因によっては必ずしも株価が上がるとは限りません。過去には、物価が上昇したのに株価は下落した局面もありました。
分散投資では、値動きの特徴が異なる資産の保有が推奨されます。
株式と不動産はどうかといえば、ある程度の相関があるといわれています。もっとも、どちらも完全に同じ要因で値動きするわけではありません。片方が上昇し、片方は下落する局面もあり、値動きのスピードも異なります。
そうしたなかで、インフレに関しては、やはり実物資産である不動産が強いといわれています。いくら大きな利益を期待できる株式であっても、インフレ下では必ずしも株価が上昇するとは限りません。
物価が上昇基調にある今、ポートフォリオに実物資産である不動産を組み入れる意義が大きくなりつつあるといえるでしょう。
メリット3. 値動きが少なく安心感がある
株価の動きの大きさについては、これまでお伝えしてきたとおりです。短期的に大きな利益を得られる可能性がある一方で、急激な下落に見舞われることもあります。日々の値動きに気を揉む投資家も少なくありません。

不動産も景気や需給の影響を受けて価格が変動しますが、不動産クラウドファンディングは少し性質が異なります。運用期間中は、基本的には市場価格に左右されず、出資額が変動しません。出資後は配当の受け取りと元本の償還を待つのみです。
なお、「みらファン」は、これまで元本割れや償還遅延がゼロの実績を積み上げてきました。安心感を重視した思想のもと、投資家が落ち着いて資金を投じられる商品を設計しています。
その代わりに、不動産クラウドファンディングは中途解約も基本的にはできません。出資金は満期まで拘束されます。ただし、不動産クラウドファンディングでは運用期間が1年以内と、比較的短期のものが多くみられます。10年単位での取り組みが一般的な実物不動産投資とくらべれば、始めるハードルは低いでしょう。満期を迎えるたびに次のファンドを探す手間はかかってしまいますが、より条件のよいファンドに乗り換えながら運用できる点は魅力ともいえます。
相場の動きをこまめにチェックしつつ利益を得る株式投資の片手間で、のんびり資産を運用できる点が不動産クラウドファンディングの持ち味です。
まとめ
株式は期待リターンの大きさが魅力ですが、値動きが大きいため資産の一極集中はリスクも高まります。その分散先として不動産、投資手法として不動産クラウドファンディングは有力な選択肢となるでしょう。まずは小額から初めて、ポートフォリオの分散を図ってみてはいかがでしょうか。
不動産(不動産クラウドファンディング)は、安定したインカムゲインを得られ、インフレに強い点も魅力です。さらに、株式投資と違って日々の値動きに振り回される心配も抑えられます。株式が持たない性質を補完する役割を果たします。
当社では、1口1万円から始められる不動産クラウドファンディング「みらファン」を提供しています。
- 投資したい物件を選ぶことができる
- 少額から手軽に投資が可能
- 利回りが比較的高い
- 不動産管理に関する手間が不要
- リーシングに関する対応は事業者側が行う
- 運用中の資金の上下が無い
- 優先劣後構造で投資家を保護
「みらファン」で手軽に不動産投資を始めてみませんか。
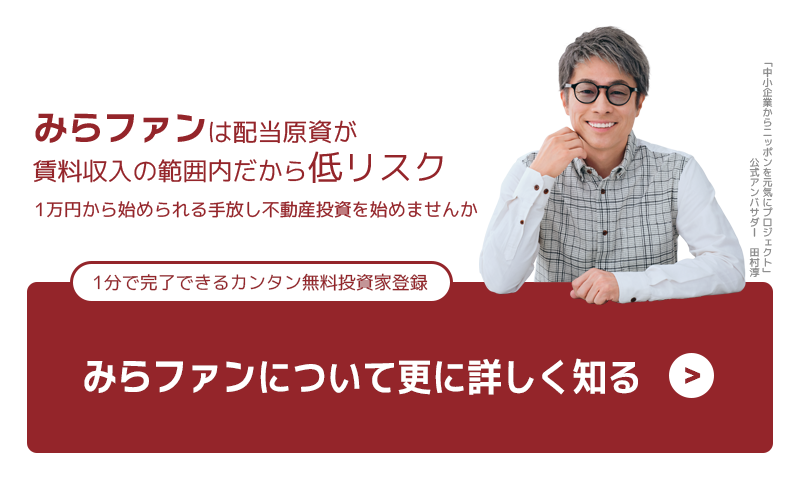
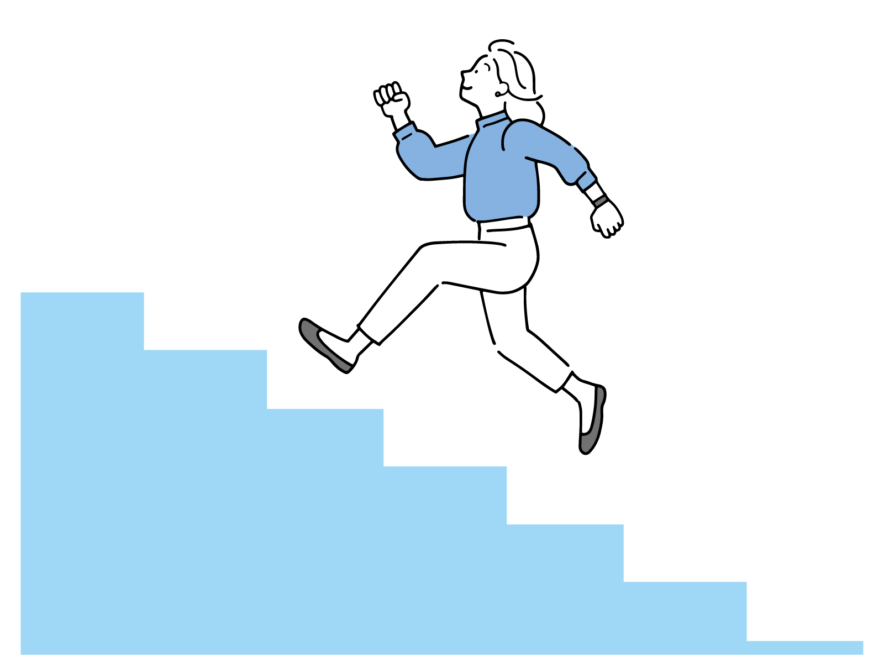










コメント